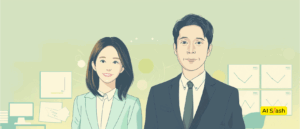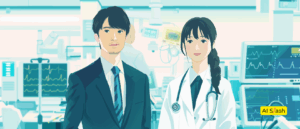はじめに|AIをめぐる“発言”の時代へ
2025年春。AI業界では新たな技術のリリースが続く一方で、それ以上に注目されているのが「誰が、どんな言葉を発したか」です。
テクノロジーの進化は指数関数的に加速していますが、その方向性を決めるのは、経営の意思、社会の倫理、組織の判断。
今やAIをめぐるリーダーの言葉は、単なるポジショントークではなく、「未来に対する投資と警鐘」として極めて大きな意味を持ちます。
本稿では、2025年3月〜4月に登場したAI業界の主要5人のキーパーソンの発言と行動をピックアップ。そこに通底する「本質的な問い」と「未来の行方」を、AI Slashの視点で読み解きます。
1. アンディ・ジャシー(Amazon CEO)
AIへの投資は“顧客中心主義”の再設計
人物紹介
クラウド部門AWSを立ち上げ、Amazonの中核ビジネスへと育て上げた構造改革の担い手。2021年のCEO就任以降は、AI戦略を「顧客基盤の拡張装置」として位置づけています。
発言概要
2025年4月10日の年次株主書簡にて、以下のように述べました:
“Generative AI will fundamentally reshape how our customers build, run, and optimize their business.”
(生成AIは顧客のビジネス構築・運用・最適化の根幹を変える)
ジャシー氏は、生成AIを単なるツールではなく、事業構造の再設計そのものと位置づけています。BedrockやAnthropicとの連携を通じ、顧客企業に“考えるAI”を提供しはじめています。
ファクト
・Amazon Bedrock導入企業数:前年比2.5倍(2025年3月時点)
・Alexaの次世代モデルにClaude(Anthropic製)を搭載予定
・AI関連投資:2025年年間予算 200億ドル超【公式発表】
注目すべき視点
AIを「効率化の道具」ではなく、「顧客の成長基盤」と捉える構図。自社の利益ではなく、顧客の成果を逆算する設計思想は、AI経営の次なる定石となるかもしれません。
2. デミス・ハサビス(Google DeepMind CEO)
AIの創造力と責任の境界を問う
人物紹介
神経科学・ゲーム・倫理工学を横断する異色の研究者。DeepMind共同創業者として、AlphaGoやGeminiなどを主導しつつ、AIと人間の「共存可能性」に執着する思想家。
発言概要
GoogleのAI映像生成モデル「Veo 2」の発表に寄せて:
“The frontier of generative video is not just technological—it’s philosophical.”
(生成映像の最前線は技術ではなく、哲学にある)
Veo 2は自然言語から60秒以上の高解像度映像を生成可能。ハサビス氏は、その強力さゆえに「倫理設計」が必要だと語り、全ての生成映像に識別コード(SynthID)を埋め込む構想を明かしました。
ファクト
・Veo 2発表:2025年4月、最大1080p/60秒に対応
・生成映像には全件にSynthIDを自動挿入(Google公式発表)
・DeepMindはGemini UltraやImagen 3にも技術提供中
注目すべき視点
AIの創造性を制御する責任は、技術者ではなく社会全体にある──というメッセージ。技術の「速さ」ではなく、「関係性の設計」に視点を戻す姿勢に、今後のAI実装のヒントが宿ります。
3. ケリー・ロマック(ServiceNow VP)
エージェント型AIの台頭と社会実装
人物紹介
ServiceNowにてエージェント型AIの事業戦略を統括。「働き方のOS」へのAI統合を進め、実装主義に基づく設計と制度化の両立を目指す、現場起点のAI推進者。
発言概要
グローバルテックフォーラム(2025年4月)にて:
“Agentic AI is no longer a prototype—it’s how work will get done.”
(エージェント型AIは試作ではなく、業務の構成要素になった)
カスタマーサポート、ITインフラ、ワークフロー設計など、目立たないが膨大なバックエンド業務が、エージェントAIによって急速に自動化されつつあると説明。
ファクト
・社内13部門でAIエージェント本番導入済(2025年Q1)
・ITサポートコスト:前年比29%削減
・ServiceNow新規顧客獲得数:前年比1.8倍(2025年3月)
注目すべき視点
重要なのは技術ではなく、文化。「AIが意思決定しうる状況」で組織がどう振る舞うか。単なる導入でなく“責任の委譲設計”が必要だとする姿勢は、どの業種にも共通する問いとなる。
4. ジョン・K・トンプソン(The Hackett Group)
生成AI導入の戦略設計と変化の測定
人物紹介
『Building Analytics Teams』の著者として著名。戦略設計とKPI評価を統合する実務家で、現在は生成AI導入における測定フレームの提唱をリード。
発言概要
The Hackett Groupの記者発表(2025年4月)にて:
“GenAI doesn’t deliver value by magic. It requires design, measurement, and cultural commitment.”
(生成AIは魔法ではなく、設計・測定・文化があってこそ価値を生む)
KPIなき導入、現場不在の戦略、PoC疲れ──それらの反省をふまえ、測定可能な行動設計の必要性を強調しました。
ファクト
・2025年春、企業15社が新プログラムを導入
・KPIには「業務再設計率」「AIタスク自動化比率」などを設定
・初年度平均ROI:1.6倍を見込む(Hackett試算)
注目すべき視点
生成AIの定着は、“使う技術”ではなく“変わる文化”を育てること。習慣化・可視化・測定を経営に組み込む設計力こそが、競争優位の差を生み始めています。
5. ウェンデル・ウォラック(AI倫理学者)
AIと倫理の交差点で“問い”を立て続ける
人物紹介
エール大学を拠点に活動するAI倫理学の権威。国連やOECDの倫理設計にも関与し、技術社会における「問いの立て方」を投げかけ続ける思想的ファシリテーター。
発言概要
ジュネーブ・AI人権会議(2025年3月)にて:
“AI may be the most powerful tool we’ve ever created. But it is also the least governed.”
(AIは最も強力かつ、最も統治されていない技術である)
企業や国家が生成AIの活用を加速するなか、倫理と透明性の欠如が「信頼性の空洞」を生んでいると警告。責任ある開発体制の制度化を訴えました。
ファクト
・国連AI倫理委員会・OECD AI倫理フレーム策定に助言中
・2025年『Ethics in the Age of Artificial Intelligence』出版予定
・全ての生成物に説明責任を求めるルール設計を主張
注目すべき視点
倫理とは抑制ではなく“問いを立て続ける文化”。AIが社会基盤となる時代において、「使うこと」よりも「何のために使うか」が企業の信用力を左右する時代が到来しています。
要点整理
- Amazon:生成AIは「顧客構造を支える装置」へ
- Google:映像生成は「責任ある創造性」への問いかけ
- ServiceNow:エージェント型AIは現場構造の再設計装置
- Hackett Group:定着には測定・習慣・設計の三位一体が不可欠
- ウォラック:倫理は抑制でなく「社会との関係設計」の核
考察と展望|問いを立てられる組織こそが、AIを活かす
AIがインフラ化する時代において、差が出るのは「どれだけ使えるか」ではなく、「どんな問いを持って向き合うか」です。
今回紹介した5人はいずれも、ツールやモデルの優劣ではなく、「何のためにAIをどう活かすか」という構造設計の問いを私たちに突きつけています。この問いに向き合う力──それこそが、2025年以降の組織の持続可能性を決める“知の資産”となるでしょう。
参考・出典
https://www.reuters.com/technology/amazon-ceo-sets-out-ai-investment-mission-annual-shareholder-letter-2025-04-10
https://www.wired.com/story/google-veo-ai-video-generator-release
https://www.axios.com/local/phoenix/2025/04/14/ai-workplace-future-agentics-robots
https://www.swissinfo.ch/eng/ai-and-human-rights-global-conference-2025