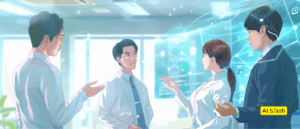はじめに
1974年──
個人が初めて「機械」と関係を結びはじめた、この年は後に続くすべてのテクノロジー史の起点だった。
米国ではAltair 8800という名のマイクロコンピュータが誕生し、のちのMicrosoft創業者ビル・ゲイツが初めてその上で動くBASICを開発。Appleも、まだガレージにあった。人類が情報処理装置に“触れる”時代が、ここから静かに始まっていた。
この10年間で、テクノロジーはそれまでの「軍や政府、大企業が使う装置」から、「個人が日常で関わるツール」へとシフトしていく。まさに“パーソナル化”の始まりだ。コンピュータは机の上に、電卓はポケットに、ゲーム機はリビングに。そして情報処理という営み自体が、誰もが担えるものとして社会に開かれていった。
一方、日本では“マイコン”という言葉が市民権を得た時代だった。1978年にはNECがPC-8001を発表し、1983年には任天堂がファミコンを発売。家電量販店が情報化の窓口となり、「個人で機械を買う」「個人で操作する」という文化が静かに根づいていく。
この10年をひとことで表すなら、「個人と機械の関係が、初めて対等になり始めた時代」。その接点が“遊び”や“趣味”であったことも象徴的だろう。何かのためにではなく、“触ってみたい”という衝動こそが、次の技術時代を導いていく原動力だった。
■ 要点整理
・「個人の知識・判断」を支える道具としてのテクノロジーが萌芽した時代
・Altair 8800(1974)、Apple I(1976)など“個人のための計算機”が出現
・Microsoft創業(1975)、Apple創業(1976)、IBM PC登場(1981)
・日本ではPC-8001(1979)やMSX(1983)、ファミコン(1983)が象徴的製品に
機械に“触れること”が個人の日常に組み込まれ始めた
世界の視点(1974〜1979)── 個人が機械に触れ始めたとき
1974年、マイクロプロセッサの価格が劇的に下がり、一般消費者にも届く時代が始まった。これがパーソナルコンピュータ時代の夜明けだった。
Altair 8800の登場は、単なる“キット販売用の金属箱”ではなく、「誰でも情報を処理できる時代の象徴」となった。全米の電子工学マニアがこの機械に熱狂し、それを見たビル・ゲイツとポール・アレンは、初のAltair向けBASICを開発、のちにMicrosoftを創業することになる。
一方、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックは、Apple I をガレージで組み立て、1976年に Apple を設立。翌年にはプラスチック筐体にキーボードと画面出力機能を備えた Apple II を発表し、ビジネス層にも衝撃を与えた。
この5年間で目立つのは、「中央集権的な巨大システム」から「個人端末へのシフト」が確実に始まったことだ。かつて計算とは大型メインフレームや研究所で行うものだった。それが“自宅でできる”という思想に変わった。
さらに注目すべきは、ユーザーコミュニティの誕生だ。ホームブリュー・コンピュータ・クラブ(Homebrew Computer Club)では、情報を共有し合い、ハードウェアを自作し、コードを分け合う文化が生まれた。これはのちのオープンソース運動やハッカーカルチャーの源流ともなる。
当時の米国社会では、ベトナム戦争後の反体制ムード、個人主義の高まり、DIYカルチャーの浸透といった背景があり、これらがパーソナルコンピューティングの価値観と重なっていく。
「政府や大企業が作ったものに頼らず、自分で組み立て、操れる技術」──これこそが、70年代後半に根づいた最初の“デジタル市民”の思想だった。
日本の視点(1974〜1979)── 教育・家計・娯楽に現れた“家庭テクノロジー”の萌芽
1970年の大阪万博を経て、日本は“技術と未来”への期待が社会全体に浸透した時代に入っていた。
「科学技術が豊かさをもたらす」という信仰が、家庭にも企業にも広がり始めたのが1974年以降の流れである。
とはいえ、当初の“機械との出会い”はあくまで企業内の話だった。1975年、NECが日本初のマイクロコンピュータキット「TK-80」を発売。個人向けではなかったが、電子工学を志す学生や研究者にとっては衝撃的なプロダクトだった。実際、このTK-80は後の多くの日本人技術者の“原体験”として語られる。
そして1976年、シャープが世界初の液晶電卓を開発。これは“持ち歩ける知性”の象徴としてヒットし、会社員や主婦層にまで浸透していく。つまり、この時代の日本におけるテクノロジーとの出会いは、「働く大人が使う道具」から始まり、「家族全体が使える機器」へと広がっていくフェーズだった。
家庭では電子ゲームが台頭し始める。1978年には任天堂が「ブロック崩し」を発売、セガもアーケード筐体で存在感を強め、遊びが“電子化”されていく。ソニーのウォークマンも1979年に登場し、“個人と機械”の距離がぐっと縮まった。
またこの時期、テレビがほぼ全家庭に行き渡ったことで、「情報は家庭の中にあるもの」として定着。学校ではラジオ体操や視聴覚教材にビデオが使われ始め、「テクノロジーを介して知る」体験が当たり前になっていく。
日本はこの時代、まだ“生産する側”であって、“創造する側”ではなかったかもしれない。だが、大量生産・大量普及の技術インフラを社会全体に張り巡らせたという点では、確実に次のフェーズを準備していたと言える。
個人と機械の最初の接触点が、教育・娯楽・家計といった生活の延長にあった日本。これが後に世界でも特異な「家庭内テクノロジー文化」を生む土壌となっていく。
世界の視点(1980〜1984)── コンピュータの民主化とGUIの夜明け
1980年代に突入すると、パーソナルコンピュータは「試作機」や「ホビー」から、「生活や仕事のツール」へと明確に変化し始めた。
1981年、IBMが初のパーソナルコンピュータ「IBM PC」を発表。OSには当時無名だったMicrosoftのMS-DOSを採用した。この出来事は、“大企業が個人向けコンピュータに本気を出した”瞬間として象徴的である。そしてこの選択が、Microsoftを世界最大のソフトウェア企業へと押し上げる布石となった。
IBM PCは「クローン(互換機)」を生み、CompaqやDellなどの後続企業が市場に参入。価格競争が進み、PCは一部の技術者のものから、一般ビジネスマンのものへと浸透していく。ここで初めて、“コンピュータを持たないことが不利になる”という状況が現れた。
また1983年には、Appleがグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を備えた「Lisa」を発表(高価すぎて商業的には失敗)。だが翌1984年、Macintoshが登場し、“画面を見ながら操作する”という概念が一般層にも認知され始める。スティーブ・ジョブズが「1984」CMで象徴的に語ったように、これは「コンピュータの民主化」の宣言でもあった。
一方でこの時期、中国はまだ改革開放の初期段階にあり、IT技術の大衆化は見られなかった。欧州ではAmstradやSinclairが安価な家庭用PCを展開し、「教育の道具」としての普及が一部進んでいたが、米国ほどのスピード感はなかった。
社会的には、冷戦構造の緊張が続きながらも、テクノロジー分野は非政治的空間として成長を続けた。「誰もが触れる技術」が、初めてグローバルに共有される下地ができつつあった──
すなわち、「情報技術が国境を越える時代」の序章がこの5年間だったと言える。
日本の視点(1980〜1984)── ファミコンとワープロが生んだ“操作文化”の始まり
1980年代前半、日本の家庭や職場、教育現場にはっきりとした変化が訪れる。テクノロジーが“見るもの”から“触るもの”へと姿を変えた時代だ。
1981年、NECは16ビットのパーソナルコンピュータ「PC-9801」を発売。これが後に“国民機”と呼ばれるほど広く普及することになる。さらに1983年、家庭用パソコンの標準化を目指したMSX規格が登場。ソニー、松下、三菱、東芝など多くの国内メーカーが参入し、「家電としてのPC」が現実味を帯びていく。
そして、1983年7月15日──任天堂がファミリーコンピュータ(ファミコン)を発売。これは単なるゲーム機ではなかった。視覚と聴覚、そして“操作”によるインタラクションが、初めて子どもたちの手の中に届いた瞬間だった。
このファミコンは、後のデジタルネイティブ世代にとっての“最初のユーザー体験”となり、「機械は怖くない」「触れば反応する」「自分の操作で結果が変わる」という感覚を自然に刷り込んでいった。これは日本が“操作文化”を深く根付かせた起点でもある。
同時に、教育分野でも動きが出始めていた。1982年、文部省が「教育用コンピュータ導入推進事業」を開始し、一部の中学校でマイコン教育が実施されるようになる。パソコン教室が整備され、「キーボードを叩いて考える」子どもたちが誕生した。
企業でもOA(オフィスオートメーション)の掛け声のもと、ワープロや表計算ソフトが導入され、事務作業におけるコンピュータ活用が急拡大。シャープの「書院」、富士通の「OASYS」など、国産ワープロ専用機が広く使われた。
このように、日本社会は「見る→操作する」「知る→考える」への転換を、“生活・教育・仕事”の三層で同時に迎えていた。しかもそれは、技術者やエリートに限られた話ではなく、“大衆技術”として家庭に根づいていった点が特筆される。
横断的インサイト(1974〜1984)
“触れる”という革命が、人間の判断構造を変えた
1974年から1984年にかけて、世界は劇的な技術進化を経験した──だが、その真の革新は「個人が機械に触れた」という事実に集約される。
それまで、情報は“与えられるもの”だった。新聞、テレビ、職場の指示──いずれも、個人は受け手に過ぎなかった。
だがこの10年で、情報を“自ら呼び出し、処理し、表現する”環境が整い始めた。コンピュータにコードを書き、キーを打ち、コマンドを通じて自分の意図を伝える。この能動的な関わりこそが、以後の全てのテクノロジー利用の基盤となっていく。
特筆すべきは、この変化が「技術者」や「研究者」だけの特権ではなくなった点にある。
・米国ではAltair、Apple II、IBM PCという形で、「趣味」「教育」「ビジネス」に分岐したパソコン文化が育ち、
・日本ではファミコン、MSX、ワープロなどを通じて、「遊び」「家庭」「事務」の中で個人が機械を扱う風景が定着した。
考察と展望
「触れる技術」から「使いこなす技術」へ──次の10年が育てたもの
1974〜1984年は、“接続の時代”だった。
人と機械が初めて対等な距離に立ち、「情報を受け取るだけでなく、自ら操作する」文化が芽吹いた10年間。ここで築かれた基盤のうえに、次の10年は“インターフェースの民主化”というテーマで加速していく。
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の普及、マウスやウィンドウによる操作体系の標準化──これはまさに、「誰もが直感的に使える技術」への挑戦だった。そしてそれは、技術の進化だけではなく、ユーザー理解の進化でもあった。
AppleのMacintosh(1984)、MicrosoftのWindows(1985)、日本では富士通FM TOWNSやPC-98シリーズの進化──これらはすべて、“どのように触らせるか”という問いへの答えであり、「触れることが当たり前になった人々」への次なる提案だった。
また、教育現場でも「情報リテラシー教育」の必要性が議論され始めるなど、社会全体が“情報をどう扱うか”を問う段階へと進んでいく。次の10年で鍵になるのは、ツールと人間の「関係の質」だ。
「どれだけ使えるか」ではなく、「どう使うか」。
判断の主導権を誰が握るのか。この問いが、1985年以降、テクノロジーの次なる段階を決定づけていく。
参考・出典
情報教育 – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/情報教育
Altair 8800 – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
Apple Computer – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Apple
Microsoft – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft
IBM PC – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
MS-DOS – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
Macintosh – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Macintosh
NEC PC-8001 – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/PC-8001
NEC PC-9801 – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/PC-9800シリーズ
MSX – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/MSX
ファミリーコンピュータ – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ファミリーコンピュータ
ホームブリュー・コンピュータ・クラブ – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Homebrew_Computer_Club
オフィスオートメーション – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/オフィスオートメーション