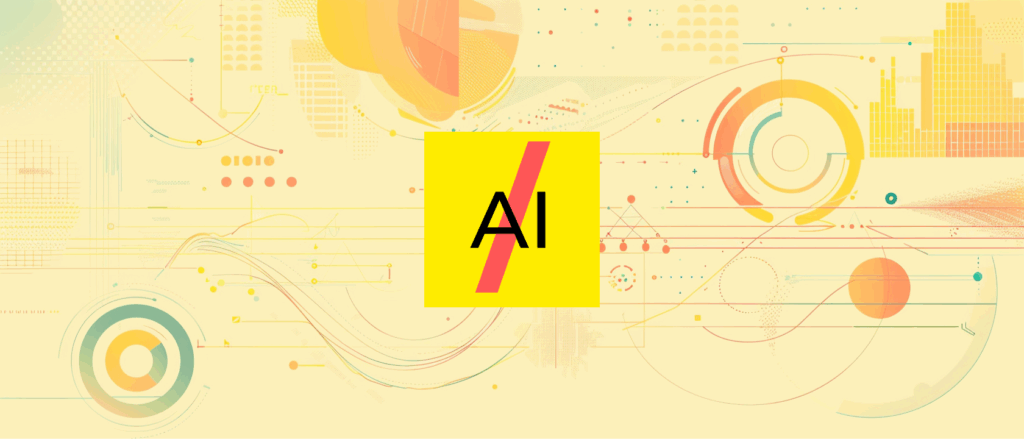AI Slash|経営に効くAIインサイト
技術が加速度的に進むいま、求められているのは “知ること” ではなく “決めること”。
AI Slash は、経営・行政の現場で意思決定を担う人のそばに立ち、AI の進化を 実務に使える構造 に変換して届けるメディアです。
私たちが解決したい課題
・情報過多 ─ 一次ソースが散在し、選別コストが高い
・抽象化の不足 ─ 技術解説は多いが、ビジネス翻訳が足りない
・導入の迷い ─ 成功/失敗のベンチマークが共有されにくい
提供する価値
・タイムリー ─ 世界の政策・資金調達・国内導入事例を 24 h 以内 に要約配信
・実務直結 ─ 記事平均読了 3 分・要点 200 字 の凝縮フォーマット
・検証可能 ─ すべての主張に 出典 URL と KPI テンプレート を付与
“/” に込めた意思

Slash( / )は本来「複数の選択肢を分かつ」記号です。
選ぶとは分けること。決めるとは迷いを断ち切ること。
私たちは、テクノロジーと現場、可能性と現実、理論と実務──その分かれ目に立ち、冷静に視点を差し出す存在でありたい。
AI Slash という名前には、そんな 「判断のあいだに立つ」 姿勢が刻まれています。
読者像
- 年商 50 億円超企業の 経営者・役員
- 事業部長/DX 責任者
- 自治体・公共政策担当者
運営ポリシー
- 中立と構造 ─ 熱狂にも悲観にも偏らず、事実から組み立てる
- 再利用可能性 ─ 読者の中で再構成され、組織に展開できる情報
- 静かな強さ ─ 決断のそばに在るメディアとして、不要な装飾は排す
編集長より
児玉 健太郎|AI Slash 編集長
「熱さ」より「構造」。現場で役立つ視点を、静かに、確実に届け続けます。
お問い合わせ
ご相談・ご連絡は info@ai-slash.jp まで。
「判断」の質を共に更新するパートナーシップをお待ちしています。